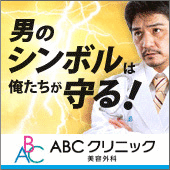プロフィール

沖縄県立宮古病院
沖縄県宮古島市は宮古列島の宮古島、池間島、大神島、来間島、伊良部島、下地島からなる市である。宮古島と池間島は池間大橋、宮古島と来間島は来間大橋、宮古島と伊良部島は伊良部大橋、伊良部島と下地島は6本の橋によって結ばれている。かつては平良市、宮古郡伊良部町、上野村、城辺町、下地町の5市町村が存在したが、2005年に新設合併して、宮古島市が誕生した。サトウキビやマンゴーなどのトロピカルフルーツなどの農業が盛んで、農業生産額は沖縄県内の市町村で1位となっている。またビーチリゾートやマリンスポーツを楽しむ観光客も数多い。
沖縄県立宮古病院は1950年に開設され、常に地域住民とともに歩んできた病院である。現在は内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、外科、消化器外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、救急科、歯科口腔外科、麻酔科、腎臓内科、総合診療科、地域診療科を標榜し、276床(一般225床、ICU4床、NICU3床、HCU4床、精神45床、結核3床、感染症3床)を有し、宮古群島における地域支援病院としての機能や役割を果たしている。
今回は沖縄県立宮古病院の本永英治院長にお話を伺った。

本永 英治 院長 プロフィール
1957年に沖縄県宮古島市で生まれる。1982年に自治医科大学を卒業し、沖縄県立中部病院で初期研修を行う。1984年に伊是名診療所に勤務する。1986年に沖縄県立中部病院と自治医科大学附属病院で後期研修を行う。1987年に西表西部診療所に勤務する。1990年に沖縄県立八重山病院に勤務する。1995年に東海大学医学部付属大磯病院リハビリテーション科に勤務し、リハビリテーション科の専門研修を受ける。1998年に沖縄県立宮古病院に勤務する。2001年に沖縄県立宮古病院リハビリテーション科部長に就任する。2011年に沖縄県立宮古病院副院長に就任する。2017年に沖縄県立宮古病院院長に就任する。
日本内科学会総合内科専門医、日本リハビリテーション医学会専門医など。
病院の沿革

- 1950年
- 宮古民政府立結核療養所として設立される。
- 1957年
- 平良市字東仲宗根807番地に木造平屋を新築移転する。
- 1960年
- 琉球政府立宮古病院に改称し、病床数が96床(一般22床、結核74床)となる。
- 1963年
- 多良間、佐良浜、来間、池間の各診療所が宮古病院管轄下に置かれる。
- 1967年
- 精神科(50床)を新設する。
- 1972年
- 沖縄返還に伴い、沖縄県立宮古病院と改称する。
- 1973年
- 146床(一般48床、結核48床、精神50床)に増床する。
- 1976年
- 本館を竣工し、195床(一般126床、結核19床、精神50床)となる。
- 1982年
- CT装置を導入する。
- 1984年
- アンギオを導入する。
- 1985年
- 人工透析を開始する。
393床(一般286床、精神100床、結核7床)に増床する。 - 1995年
- 高気圧酸素治療を開始する。
- 2001年
- MRIを導入する。
精神科デイケアを開始する。 - 2003年
- 地域連携室を開始する。
- 2004年
- 精神科作業療法を開始する。
初期研修医の受け入れを開始する。 - 2006年
- ICUを開設する。
精神科開放病棟(精神50床)を閉鎖する。 - 2009年
- 沖縄県立看護大学・大学院宮古教室を開所する。
- 2011年
- 新宮古病院の起工式を行う。
- 2013年
- 新宮古病院が開院する。
- 2014年
- 入院支援室を開設する。
- 2015年
- 地域がん診療連携拠点病院に認定される。
家庭医療センターを設置する。
臨床研修病院(1)基幹型に認定される。 - 2017年
- GCU(6床)を開設する。
- 2018年
- 眼科外来を再開する。
- 2020年
- 多目的血管撮影装置(バイプレーン)導入、急性期脳卒中センターとして脳血管内治療を確立する。
沖縄県立宮古病院の前身は結核療養所で、まだ沖縄が占領下にあった頃、宮古民政府が開設したものである。
「開設されたのは私がまだ生まれていない頃です(笑)。その当時のことはよく知らないですね。でも私が中学校や高校に通っていた1972年から76年にかけて、新聞紙上に医師不足の記事がよく載っていたことは覚えています。医師が6人しかいなかったときもあったようです。」
その後、精神科も併設された。
「今も精神科病床を持っています。当院はそうした精神科病床と共存している総合病院なのです。」
沖縄の返還とともに沖縄県立宮古病院となり、診療科目や病床数が増加する。そして、2013年には念願の新病院へと新築移転を実現させた。
「新病院を目の当たりにして、時代の変わり目を見たような気がします。旧病院の老朽化に伴い、1998年頃から新しい病院にしたいという宮古島市民と当院の医療職の人たちの願いがあって、ずっと運動してきました。実現には長くかかりましたが、ようやく計画が承認されて、2013年6月1日にオープンできました。そのときに初めて当院に電子カルテが導入されるなど、色々な改革がありました。」
新病院は沖縄県立宮古農林高校の跡地である。
「移転にあたってはいくつか候補地がありました。農林高校が翔南高校と統合し、宮古総合実業高校になったので、農林高校の跡地が候補になったのです。県の土地だということで、県の教育委員会から通常よりもかなりリーズナブルに譲っていただきました。高校ですから、運動場が広かったのも良かったですね。しかし空港のそばにここよりも2倍ほど大きな土地があり、価格も無料だと聞いたのですが、そこは海までの距離が長かったのです。そうすると産業廃棄物や汚染水処理などの排水工事にお金がかかりますから、難しいだろうということになりました。一方で、この場所は平良港に近く、宮古島市内に位置しているので、高齢者を含めて、誰でも受診しやすい場所です。こちらの場所だと外来患者さんも減りませんでしたし、結果として良い立地を得ました。」
新しい病院になって、様々な変革があった。
「電子カルテ導入では業務が質的に改善しました。また、新病院とともに新しい臨床研修制度も始まりました。それまでの当院は協力型の臨床研修病院だったのですが、基幹型に昇格したのです。初期研修に加えて、専攻医研修でも総合診療科の基幹型病院として認められました。それ以来、初期研修医も専攻医も毎年、当院に来ています。日本全国の離島の病院の中で基幹型研修病院となった病院は珍しいですし、日本最南端の基幹型研修病院なのではないでしょうか。」