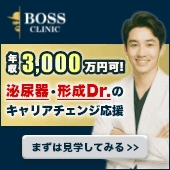医師の転職市場2025年版
2025年、医師の転職市場は医療政策の変化や働き方改革の影響を受けて大きく動いています。本記事では、診療科別・年代別に転職の傾向を読み解き、成功するための視点と戦略を解説します。
2025年の医師転職市場の全体傾向:医療政策と労働環境の変化を背景に

2025年を迎え、医師の転職市場には大きな変化が生まれています。背景には、少子高齢化による医療ニーズの変化に加え、医師の働き方改革が本格化していることが挙げられます。特に、労働時間の制限やワークライフバランスへの意識の高まりが、医療機関側の採用スタンスにも影響を与え、週4日勤務、当直なし、時短勤務といった柔軟な雇用形態の求人が増加しています。
また、新型コロナウイルスの流行を経て、感染症対策や在宅医療、遠隔診療といった分野のニーズも拡大しました。その結果、都市部だけでなく地方でも、診療体制の再構築が進み、医師の配置を見直す動きが広がっています。これにより、都市部から地方へのUターン・Iターン転職も活発化しています。
一方で、若手医師を中心に「専門性よりも働きやすさを重視する」転職希望者が増加傾向にあり、医療機関は従来の待遇重視から、職場環境や勤務内容の柔軟性を訴求する姿勢へと変わりつつあります。転職市場は医師優位な状況が続いており、自らのライフスタイルやキャリア志向に合った職場を選びやすい時代となっているのです。
診療科別の求人動向:需要が伸びている科、停滞している科とは?

2025年現在、診療科ごとの求人動向には明確な差が見られます。特に需要が高まっているのは、内科系(一般内科、訪問診療を含む)、整形外科、精神科、皮膚科などの分野です。これらの科目は高齢化や慢性疾患の増加、メンタルヘルスへの関心の高まりといった社会的背景と深く結びついており、全国的に求人が増加しています。
中でも精神科と訪問診療の需要は顕著で、特に地方では「常勤で在宅対応可能な医師」を求める医療機関が目立ちます。また、皮膚科や美容皮膚科も都市部での人気が高く、週3~4日勤務や時短勤務の求人も増加しており、女性医師の転職先として注目を集めています。
一方で、需要が停滞しているのが小児科や産婦人科といった科目です。医師の負担が大きく、当直や夜間対応が避けられないことから、敬遠されがちです。また、病院側も採用に慎重な姿勢を見せており、充足傾向にある地域では求人が少ないケースもあります。
このように、診療科ごとの転職市場には偏りがあるため、自分の専門性と市場のニーズを照らし合わせながら、将来的なビジョンを持って職場選びを行うことが重要です。
20代・30代若手医師の転職傾向:柔軟な働き方とスキルアップ志向

20代・30代の若手医師の間では、キャリア初期から転職を視野に入れる傾向が強まっています。かつては「まずは医局に所属し数年勤務してから考える」という流れが一般的でしたが、現在では研修終了後すぐに転職を検討する医師も増えており、医局に依存しないキャリア志向が主流となりつつあります。
この世代の医師が重視するのは、給与や肩書きといった従来の価値観よりも、「柔軟な勤務形態」「ワークライフバランス」「多様な経験を積める環境」といった点です。週4日勤務や当直なし、外来のみのポジションなど、働き方の自由度を重視して転職先を選ぶケースが目立ちます。
また、複数の診療科を経験したいという希望や、美容医療や産業医、在宅医療など新たな分野にチャレンジする意欲も高く、短期間で複数の職場を経験することへの抵抗感もあまり見られません。転職が「リスク」ではなく「選択肢の一つ」と捉えられているのです。
とはいえ、経験が浅いことからポジションや条件の交渉が難しい面もあるため、キャリアアドバイザーなど第三者の支援を活用して情報収集と自己分析を丁寧に行うことが、納得できる転職を実現する鍵となります。
40代・50代の中堅・ベテラン医師の転職:安定志向と管理職志向の二極化

40代・50代の医師における転職は、キャリアの成熟とともに目的が多様化しています。管理職や院長職といったポジションを狙うマネジメント志向の医師や、専門領域をさらに深めるために大学病院や研究機関への移籍を検討するケースもあります。また、育児や介護をきっかけに地元へのUターンを希望する「生活再設計型」の転職も増加傾向にあります。
この年代の医師は、豊富な臨床経験と人脈を活かして、より責任のあるポジションを希望することが多い一方で、体力的な負担を考慮して当直なしや時短勤務を希望するケースもあります。特に地方医療機関では、ベテラン医師の診療能力を高く評価しており、院長候補として迎えたいという求人も多く見られます。
また、「これまでの臨床経験を地域貢献に活かしたい」という志を持ち、診療だけでなく地域保健事業や自治体連携などにも関心を示す医師も少なくありません。収入やポジションに加え、「どのように医師人生を終えるか」を意識する時期でもあり、転職先には「生き方」としての価値を求める傾向が強くなります。
この年代での転職は、家族との相談や今後のライフプランと密接に関わるため、短期的な条件だけでなく中長期的な視点で職場を選ぶことが重要です。
働き方改革が医師の転職に与える影響:週4日勤務・当直なし求人の増加

医師の転職先を考えるうえで、「都市部」と「地方」のどちらを選ぶかは大きなポイントです。両者の求人内容や働き方には明確な違いがあり、自分のライフスタイルやキャリア志向によって適した環境が異なります。
都市部の求人は、診療科や勤務条件が細分化されており、専門性の高い診療に集中できる環境が整っています。最新の医療設備や研究体制が整っている病院も多く、学会発表や研修の機会にも恵まれています。一方で、競争が激しく、勤務時間が長くなりがちなことや、当直・オンコールが多いなどの負担が伴う職場も少なくありません。
対して地方では、医師不足の影響から、総合診療的な役割を求められるケースが多く、幅広い症例に対応する機会があります。また、患者との距離が近く、地域に根ざした医療を実践できる点が魅力です。勤務条件も柔軟で、週4日勤務や当直なしのポジションなど、ワークライフバランスを重視した働き方が可能な職場も多く存在します。
さらに、地方勤務は年収面でも好条件が提示されることが多く、赴任手当や住宅支援などの手厚い待遇が用意されていることもあります。とはいえ、医師一人あたりの負担が大きくなりやすいため、事前に業務内容や体制をしっかり確認することが大切です。
都市と地方、それぞれの環境にメリットと課題があるため、自身のキャリアステージや生活環境に合わせた選択が求められます。
女性医師の転職トレンド:育児・介護と両立できる職場への注目

医師が転職活動を行う際、転職エージェントの活用は非常に有効です。自分一人では見つけにくい非公開求人の紹介や、条件交渉のサポート、医療機関との日程調整などを無料で行ってくれるため、時間のない医師にとって心強い味方となります。
まず、信頼できるエージェントを選ぶことが成功への第一歩です。医師専門のエージェントであること、医療業界に詳しいキャリアコンサルタントが在籍していること、そして自分の希望にしっかり耳を傾けてくれる姿勢があるかどうかが、選定時のポイントとなります。できれば複数のエージェントに登録し、相性や対応の質を比較検討することも有効です。
エージェントを利用する際には、自分の希望条件を明確に伝えることが重要です。給与や勤務時間だけでなく、将来のキャリアビジョンや生活スタイルも含めて共有することで、より精度の高いマッチングが可能になります。また、エージェントは医療機関の内情や職場の雰囲気といった、求人票では分からない情報を持っていることが多いため、積極的に質問して活用する姿勢が求められます。
注意すべき点として、エージェントによっては紹介先との関係性を優先し、求職者の希望とマッチしない求人を勧めてくる場合もあります。そのため、自分の軸をしっかり持ち、疑問点は遠慮せずに確認する姿勢が大切です。
転職エージェントはあくまで「支援者」であり、最終的な意思決定は自分自身です。信頼できるパートナーとともに、納得のいく転職を実現していきましょう。
医師専門転職エージェントの活用法:成功する情報収集と交渉術

医師の転職は、専門性の高さや職場環境の多様さから、慎重な判断が求められます。しかし、実際には「思っていた職場と違った」「待遇にばかり注目してミスマッチだった」などの失敗も少なくありません。こうした事態を防ぐためには、事前の情報収集と自己分析が重要です。
最も多い失敗の一つが、「条件の良さ」だけで職場を選んでしまうケースです。たとえば、年収が高いからといって即決してしまい、実際に働き始めてから当直回数の多さや人間関係のストレスに気づくこともあります。給与や勤務日数といった数値だけでなく、チーム体制、教育制度、院内文化など、質的な要素も重視することが肝心です。
また、自己分析が不十分なまま転職を進めた結果、「自分のキャリアビジョンに合わなかった」という後悔も少なくありません。どの診療科でどのような専門性を伸ばしたいのか、将来開業や管理職を目指しているのかといった目標を明確にし、それに沿った職場選びをすることが大切です。
内定をもらった医療機関には、可能であれば事前に見学や面談を依頼しましょう。現場の雰囲気や実際の働き方、スタッフ同士の関係性などは、求人票だけでは判断できない部分です。職場を肌で感じることが、後悔のない転職につながります。
転職はチャンスでもありますが、失敗すれば再び短期間での転職を余儀なくされるリスクもあります。焦らず、慎重に情報を集め、自分自身の価値観と照らし合わせながら進めていくことが、成功のカギとなるのです。
2025年以降に向けたキャリア設計:将来を見据えた転職戦略とは

2025年以降の医師転職市場は、大きな転換期を迎えると予測されています。少子高齢化の進行や医療需要の地域格差、デジタル技術の導入などにより、従来の医師像や働き方に変化が求められているからです。このような環境の中でキャリアを築くには、長期的な視野を持った戦略が必要不可欠です。
まず、今後も高齢者医療と地域医療の需要は増加する見込みです。在宅医療や慢性疾患の管理といった分野では、総合診療スキルを持つ医師のニーズがさらに高まるでしょう。一方で、都市部の急性期病院ではAIや遠隔診療の導入が進み、効率化と専門性の両立が求められる時代になります。
こうした変化に備えるには、「専門性の深化」と「柔軟性のある働き方」の両立がカギとなります。たとえば、週4日勤務で働きながら、自分の専門分野に関する研究やスキルアップに時間を使う医師も増えています。また、医療ベンチャーや行政医療、教育分野など、病院外での活躍の場も広がっており、「医師=臨床」という枠にとらわれないキャリア形成が可能になってきました。
さらに、複数の職場を掛け持ちする「ポートフォリオワーカー型医師」や、「オンライン診療+地域診療」など、働き方の多様化も進んでいます。自分の専門性や志向を軸に、柔軟な働き方を模索することで、変化の激しい医療界でも安定したキャリアを築くことができるでしょう。
今後の転職市場では、「即戦力」だけでなく、「持続可能な働き方」や「将来性」が評価される傾向が強まります。2025年以降も活躍できる医師であるために、自分の強みを見つけ、長期的なキャリア設計を意識した転職戦略を立てていくことが求められるのです。