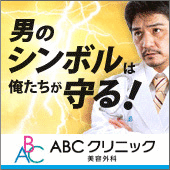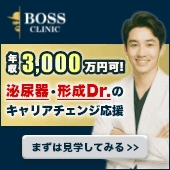岩手県大船渡市に在住のAさんが発見されたのは、東北といっても日が高い日中は燦々と陽が照りつける、三陸鉄道南リアス線綾里駅前に広がる台地の片隅だった。片岡警部が額の汗を拭いながら、東京から派遣された検死官の北村と病理学者の鈴木に話しかける。
- 片岡
- 「何歳くらいの人ですかね」
- 北村
- 「恐らく30代後半、骨格から見て女性ですね」
- 片岡
- 「歯が欠けてますね」
- 鈴木
- 「この地域では、成人になる時に歯を折る習慣があると聞いている。下顎の左側の奥歯、第二小臼歯から第三大臼歯まで、歯槽の吸収があるから歯周病で脱落しているね」
- 北村
- 「外耳道に変な骨増殖がありますが。。」
- 鈴木
- 「外耳道骨腫、いわゆるダイバーズイヤー(diver's ear)だね。潜って海産物を取ってた人かも。。」
- 北村
- 「あまり見ない首飾りをしてますね」
- 片岡
- 「これはイノシシの犬歯や切歯、動物の骨などからできている、当時としては大変立派な首飾だよ」
ここまで読んで、あれ?と思った読者も多いと思う。土曜サスペンス風に、死体が埋められた事件現場の話に置き換えて少し脚色してみたが、Aさんというのは、実は宮野貝塚遺跡から発見された「F地区出土人骨」である。「縄文人の死生観」の著者の山田康弘氏がこの人骨を見て詳しく分析していて興味深い。

Aさんは、縄文時代の中期に亡くなった女性とみられる。縄文時代に医療技術と呼べるものがあったかどうかは難しいが、祈祷や呪いが今でも未開の原住民の中で行われているように、縄文時代に病気や怪我の治療行為の一環として、装身具の着装が行われていた可能性は高い。山田氏はこの遺体を見て以下のような感想を述べている。
このように考えていくと、動物の歯牙等を素材とする装身具のなかには、動物たちの鋭い武器をもって辟邪(邪悪を避ける)や呪術的な医療行為に用いられたものがあったということができるだろう。また、宮野貝塚例の場合、その骨病変のあり方や装身具の質と量からみて、特殊な知識なしにこのような施術を行い得たとは思えない。とすれば、当時すでにそのような呪術を施すことができる特殊能力者、すなわち呪術医(witch doctor)が存在していたことになる。この呪術医は多くの病気の治療を、呪術や薬草などの知識を駆使して行ったことであろう。
彼女は、三〇代半ばでガンに侵された。状況からみて、おそらくは全身への転移も存在したことであろう。末期における苦しみは相当なものであったに違いない。その病魔を退散させるために、治療の一環としてイノシシ歯牙製の首飾がつけられたのであった。現代医学からみて、治療効果はほとんどなかったであろう。しかし、彼女がこれによってどれだけの「癒し」を得たことか、想像に難くない。ひょっとしたら、一時的に病状が回復したかもしれない。それがたとえプラシーボ(偽薬)効果であったとしても、生きようとする意志が結果的に延命効果をもたらすことはよく知られた事実である。しかし、さまざまな治療の甲斐なく、彼女は亡くなってしまった。治療として護符の首飾をかける。それを原始人の迷信と言って現代人が一笑に付すことは簡単だ。しかし、たとえどんなに医療技術が未熟であったとしても、そこにあるのは生に対する真摯な思いであって、決して私たちが迷信だとか野蛮なものとして排斥できるようなものではなかったはずである。彼女は精一杯生きて、病魔と闘って、そして死んだのである。一体誰が、それを笑うことができるのだろうか。
私が大学病院の研修医だった頃、1970年代後半だったが、肺癌は死の病で、手に入る抗癌剤、免疫抑制剤のほとんどは効かなかった。朝早く病棟の始業前に、肺癌研究班の班長が「今度はこれとこれを組み合わせて使ってみよう」と根拠のない当てずっぽうの処方計画を主治医に伝えることが精一杯だった。インフォームド・コンセントなどがいわれていない、パターナリズム全盛期の大学病院だったから、肺癌患者は結核病棟に入れられた。咳、血痰、呼吸苦、るい痩などの症状が似ていた為だ。「あなたは肺癌です」と主治医が真実を伝える事は「あなたの病気には治療法がなく、あとは死を待つのみです」と伝える事とイコールだった。こうした宣告をすることで、大学病院の病室から飛び降り自殺する患者が何人もいた時代だ。「それを知らせないほうが本人のため」と、医師も家族もそれを納得していた。
1万数千年という時を経ていても、縄文人あるいは縄文時代に患者を診ていた医師たちと我々とは、それほど遠い人たちではないのだ。
古病理学が解き明かす縄文時代の病変
古病理学は、人骨、特に過去の人骨を詳細に研究する学問である。最近の日本では患者が死亡した後に行われる病理解剖は減ってきてはいるが、このプロセスを経ないと解明できない死亡原因や病態・病状変化は少なくない。現在の医学的技術をもって、古代の人々の遺した直接資料である骨を診る事は、現代と同様にその人に起きた疾病の多くを知る手がかりとなる。鈴木隆雄博士はその道の専門家である。鈴木先生がどれだけのback groundを持っているか分からないと、読者はその信頼性を疑うかもしれないので、あえてその経歴を載せさせていただく。鈴木先生は1976年札幌医科大学医学部を卒業し、1962年東京大学大学院理学系研究科博士課程を修了して理学博士号を取られた。1988年には札幌医科大学に帰られて助教授となり、1990年東京都老人総合研究所研究室長(疫学)、1996年同研究所部長、2009年国立長寿医療センター研究所所長を務められている。
鈴木先生曰く「たとえば、ある縄文時代の人骨によく治った骨折の痕跡が明瞭に残っていれば、その個体はいつごろ、どのような状態で骨折し、その後どのような変形が生じ、いつごろ死亡したかということが、かなりの信頼性で判定することが出来るのである」
縄文人の骨折痕
今のように道路が整備されているわけもなく、ガードレールもない大自然の中で、鹿やイノシシを追って森や崖を駆け巡っていた縄文人にとって、怪我や骨折は日常茶飯事だっただろう。転落事故や崖崩れによる生き埋め、獣からの逆襲などもある。縄文人の骨病理からは、縄文人が「相当に厳しい状況にあった事は間違いない」ようだ。
鈴木先生によれば、「これまで報告されてきたおよそ数千体にものぼる縄文時代人骨での病変の報告でもっとも多いのは骨折であることは間違いのない事実」である。「これまでの研究を総合すると縄文時代人での骨折頻度はおよそ3〜7%と推定されている。男女比は3対1〜6対1と圧倒的に男性に多く発生している。やはり、男性の方が狩猟などの厳しい活動が多かったのであろう」との印象だ。
以下の写真は千葉県辺田貝塚から発掘された上腕骨だ。どうしてこのような一片の骨だけで性別が分かるのか、それは「上腕二頭筋の付着部の形態(筋肉量が多い男性の方が骨膜に付着する面積が広くなる)など」から推定できるのだという。この骨は「肘の関節部に変形がみられ、先端の部分が内側に偏位し、この関節部分と骨の長軸のなす角度(顆体角)は正常よりも30度内方にズレている。一部に小孔状の骨欠損と二次的な骨形成部分が併存している。また、上腕骨後面の肘関節の表面には変形性関節症による変化も併存している。これは明らかに上腕骨顆上骨折後の変形治癒の例と診断されたもので、恐らく小児期の骨折で、その後癒合と自然矯正がうまくいったものであろう」との鈴木先生の説明を読むと、この女性が子供の頃に住居の周りで木にぶら下げた蔦のブランコに乗っていて、友達がグッと押したことから転倒し、肘を強く打ってしまった様子が目に見えるようだ。「え〜ん、キキがおっぺした、いたいだば」といいながら父親に駆け寄ると、父親は患部に布を巻いて「静かにしとらんか」となだめて抱いてやったことだろう。縄文人も今の日本人も変わらない。

縄文時代のケア
最近では、独居老人の孤独死が問題になっている。日本が富国強兵、経済発展のために選択した政策のツケが回ってきたのだ。日本全国の若者を地域社会の絆から引き剥がし、工場の労働者や企業のblue workerとして社畜化した。地方は人口が減って過疎となり、高齢者ばかりの虚脱した社会となった。集められた労働者は、都市近郊の公団住宅を当てがわれたが、子供を産み育て、その子供が自立して離れて行くと老夫婦二人が残された。そのうちの1人が亡くなれば独居老人となる。東京などの大都市では、同じことが建売住宅や賃貸マンションでも起きて、地域社会との接点を持たない地方出身の流入者や社会的弱者は孤立し、人知れず死んで行く社会が完成してしまっている。
縄文時代は、それまでの石器時代に行われていた、狩猟・採取をしながら遊動する人たちが、ある特定の土地、洞窟などに定住し始めた時期である。氷期から温暖な気候に地球環境が変化すると、森林は針葉樹林から落葉広葉樹林に変わっていった。そこに生きる動物も、ナウマンゾウやオオツノジカなどの大型の獣類からイノシシやシカなどの中小型動物に変化した。縄文人は、森の木の実、鹿、猪、狐、狼、ウサギなどを狩猟・採取する、豊かな大地を手に入れたのだ。川や海では季節ごとに多くの種類の魚貝類がとれ、他の土地に移住しないでも十分な生活を営むことが出来る。食料が調達出来るかどうか分からない未知の土地に、女子供を連れて、あえて危険を冒して移り住む必要性はないだろう、そう縄文人が考えてもおかしくない。最初は洞窟に住み、そこから出て野原に竪穴を掘って住居を作った。大体30人ほどが集団で暮らしていたようだが、縦穴住宅のサイズからは親子を1単位とする「家族」で暮らしていたと考えられている。現在の未開発国と同様に、周産期死亡率は高く、出産に伴う妊産婦の死亡率も高かったから、自ずと一夫多妻となり、DNAの解析からは、近親婚が珍しくなかったようだ。アフリカのマサイ族の男性に嫁いだ永松真紀さんによれば、彼女は第二夫人であり、sexは種付けとして行われ、一瞬で終わることが大変不満だったと書いているから、縄文人も同様の生活を送っていたと推測される。子供を育て、木の実を叩いて粉にしたものを焼き(縄文クッキー)、食事の支度をして、土器を作る。獣の皮を鞣したり、木の皮や植物繊維で編み物をしたり、鹿の中手骨で作った針で毛皮の衣類を作ったりと、女性の役割は大きかっただろう。それに加えて、骨折した人のケア、先天異常を抱えて動けない子供たちのケアもしていたに違いない。

北海道西南部の内浦湾に面した虻田町(現・洞爺湖町)近くにある入江貝塚は、縄文前期末葉から後期までを含む貝塚だ。ここで発掘された「入江9号」は、思春期を迎えた頃病魔に犯され、四肢骨の発達が遅滞しただけでなく、退化現象を起こし、少なくとも数年間は四肢麻痺で寝たきりのままの状態で過ごした女性のようだ。鈴木先生は、この女性は進行性筋ジストロフィー症ではないかと推測している。そして、「全身病変の珍しさや原因疾患の鑑別はともかくとして、(ー中略ー)大きな障害があり、成人するまでの長いあいだ、寝たきりを余儀なくされたこの例は、縄文時代にあっても周囲の手厚い保護と介助を必要とした身体障害者をすでに当時の人びとが受け入れていたことを立証している。このことは、我が国の原始社会とみなされている縄文時代にあって、障害者とその介護にたいする精神世界と社会構造を知るうえで、手足の萎えた入江9号人骨は貴重な証人なのである」とコメントしている。
縄文人の手には、今の日本で手に入るケアグッズがあるはずもない。ケア理論もケアスキルもない彼らがどうやって四肢麻痺の少女の生活を長く支え、生きる糧を与えていたのだろうか。今となっては知る由もないが、今の日本、いや今の世界にはないヒトに対する深い洞察と慈愛、信頼と幸せを与える力、心、大きな「something」があったことは間違いない。
(8月号に続く)