
神津 仁 院長
1999年 世田谷区医師会副会長就任
2000年 世田谷区医師会内科医会会長就任
2003年 日本臨床内科医会理事就任
2004年 日本医師会代議員就任
2006年 NPO法人全国在宅医療推進協会理事長就任
2009年 昭和大学客員教授就任
1950年 長野県生まれ、幼少より世田谷区在住。
1977年 日本大学医学部卒(学生時代はヨット部主将、
運動部主将会議議長、学生会会長)
第一内科入局後、1980年神経学教室へ。
医局長・病棟医長・教育医長を長年勤める。
1988年 米国留学(ハーネマン大学:フェロー、ルイジアナ州立大学:インストラクター)
1991年 特定医療法人 佐々木病院内科部長就任。
1993年 神津内科クリニック開業。
「NBMと動的平衡」
生物学者で著作家でもある福岡伸一氏の提唱する「動的平衡」とは、「それを構成する要素は、絶え間なく消長、交換、変化しているにもかかわらず、全体として一定のバランス、つまり恒常性が保たれる系」を示しているという。人間の身体は勿論の事、地球環境でさえこの動的平衡を保ちながら「存在」を保っているのだと主張する。
人間の身体でいえば、細胞は常に壊され、作られて、新しい細胞として働くことが必要となる。地球環境でいえば、窒素が再利用され、生命の連鎖が繰り返されていく。
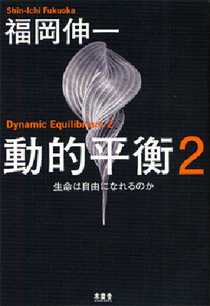
福岡氏はいう。
「なぜ常に動的なものに、ある種のバランス、恒常性が保たれうるのか。それは、バランス=恒常性を保つためにこそ、常に動いている事が必要である、ということである。この世界において、秩序あるものには等しく、それを破壊しようとする力が情け容赦なく降り注いでいる。エントロピー増大の法則である」そして、そのエントロピーの増大を防ぐためには「わざと仕組みをやわらかく、ゆるく作る。そして、エントロピー増大の法則が、その仕組みを破壊することに先回りして、自らをあえて壊す。壊しながら作り直す。この永遠の自転車操業によって、生命は、揺らぎながらも、なんとかその恒常性を保ちうる」と説明する。
我々の日常診療を振り返ってみると、この「動的平衡」をいかに患者の病態において保つことが出来るか、ということに努力をしているのだと分かる。大学病院の外来で90日処方をするということは、この「エントロピー増大の法則」に患者の病態を任せてしまっていることに他ならない。その90日の間にいろいろなことが患者に起こり、何もその事象に関与しなければ、患者の病状はますます悪化し、そのまま外来に帰って来れなくなることもあり得るのだ。患者の身近で、病状の動的平衡を保つ努力をしているのが、誰あろう地域の主治医なのだ。地域医療に携わる地域の医師たちは「かかりつけ医」といわれる。かかりつけ医が大切な所以である。
かかりつけ医は勿論医学者であるから、科学的データに基づいてEvidence based medicineを実践している。それに加えて、最近いわれるようになったNarrative based medicineを大いに実践しているのが地域医療に携わる臨床医だ。
元々これを提唱したのは英国の開業医といわれている(1998年のBMJ)。narrativeは「物語」と訳され、患者と医師が対話を通じて物語られた、患者の個々人としての背景を中心に、患者の抱えている問題に対して全人的(身体的、精神・心理的、社会的)にアプローチしていこうとする臨床手法だ。
札幌医科大学地域医療総合医学講座の山本和利教授は、そのブログで、第49回小児アレルギー学会で話をした内容をこのように書いている。
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ナラティブとは、「意味付けつつ語る」ということであり、その意味付けは多様である。そして、ナラティブに必要な技能とは、「聴く」、「理解する」、「解釈する」、「患者の苦境をその複雑さとともにまるごと把握する」の4つである。
ナラティブが扱うのは、体験であって主張ではない。ナラティブ能力を磨くことで、医師は、患者に起こった特定の出来事を、患者にとっての重大な状況や苦境として捉えることができるようになる。ナラティブの特徴は、聴き手と語り手とが相互に絡み合い勇気づけあいながら、患者に起こった出来事に意味づけしようとすることである。
ここで強調したいのは、NBM実践の方法論・テクニックに精通することによって患者とのコミュニケーションが改善し、良好な人間関係が得られると単純化して考えることは危険である、ということである。その前に、患者の生活の改善に少しでも役に立ちたいという医療姿勢がなければ、慇懃無礼な医療者に陥りかねない。そうならないためには現場で患者と一緒に悩みを共有することをたくさん体験することである。
-----------------------------------------------------------------------------------------------
私が日常診療の中で、パーキンソン病患者さんとの間でclinical strokeをしている事例を「The Life of Parkinson disease~NBMの視点から~」として述べてみたい(プライバシー保護の立場から、一部架空の描写があることをお断りしたい)。
T.A.さん 60歳(初診時)
主訴は、「左手、左足のふるえ」だ。パーキンソン病患者さんの初発症状としては一般的といっても良い。
その病歴はというと、こんな風だ。ある年の暮れから左手足のふるえに気付く。妻からも「あなた、テレビ見てボーっとしている時に、随分と手がふるえるわね。一度病院に行ってみてもらったら?」といわれ、某大学病院神経内科を受診した。大変に有名なその病院では、診てもらうのに3時間は待たなくてはならない。今は紹介状がないと特定機能病院の受診は難しいのだが、当時は「風邪をひいても大学病院に行く」という時代だった。長く待っても、とにかく「偉い先生」に診てもらいたいと思った。

(写真と本文とは無関係です)
案の定3時間ほど待たされたが、待合室に座っていたT.A.さんを看護師さんが「どうぞお入りください」と呼び入れてくれた。ドアを開けて入ると、やや広めの診察室に助手が一人教授に付いている。入室するなり、「ああ、パーキンソン病だね。ふるえはいつから?」と教授が助手に問診票を手に持ちながら尋ねた。診察は型通り終わり、アルマール20mg/日が処方された。なんだ、3時間待ってこれじゃあ近所の先生に診てもらった方がいい、と考えたT.A.さんは、当院を受診することになった。
当院での神経学的診察は、rigidity(-/-)。安静時振戦は上肢(±/++)、下肢(-/+)、Masked face(+)、Myerson’s sign(++)、歩行は正常。pulsionはante-pulsion(++)、latero(-)/(-)、retro(+++)。大学病院で診断されたのと同じ診断がついて、いよいよパーキンソン病の治療が始まった。
初診時の処方内容は、ビ・シフロール0.25mgを分2として朝夕0.125mgずつ。以後漸増して4月26日にビ・シフロール0.5mg分3として0.5mgずつ三回服用とした。それにインデラル20mg/を追加した。
以後の治療経過を記載する。ふるえが始まってから2年後に当院を受診となったcaseだが、ドーパミンアゴニストが次々と導入され、ビ・シフロールが注目されていた時期でもあり、まずはこれを使うことにした。しかし、服用して2週間後には嘔気(+)、胸がつまる感じがするとの訴えあり、ビ・シフロールを1mgに減量し、アキネトン2mg/日を追加することとなった。
服用後次第にTremorが改善し、服薬開始3ヶ月後には、安静時振戦は上肢(-/+)、下肢(-/-)と改善し、Masked face(-)、Myerson’s sign(+)、歩行は正常。pulsionはante-pulsion(-)、latero(-)/(-)、retro(±)と、hypokinesia、姿勢反射ともに改善した。
その年の10月に「夜起きた時に便器の周りにヒルが付いているように見える」との訴えがあった。幻覚が見えることは、服薬の種類によっては出てくることで、対処法としてmajor tranquilizerを使う必要がある場合がある。実際には存在しないものだから、手で触ってみるとそれが幻覚だと分かることが多い。本人には「もしへんな物が見えたら触ってみると良い」とアドバイスした。2週間の経過観察をしているうちに、幻覚は消失し、本人も安心して通院することが出来るようになった。
T.A.さんは、奥さんと一緒に彫刻をやっている。指導している先生が、良い作品が出来たから地域の展示選考会に出してみてはと勧めてくれた。多くの作品が出品される中、なんと金賞を取ることが出来た。「美術館に飾られることになったので、先生、見に来てください」と笑顔で報告に来た。
11月1日、左手のふるえをさらに止めたい、との希望あり、リボトリールを開始、漸増して1.5mg分3まで用いることにした。ふるえに対する効果はあったものの、翌年2月に「ふるえを妻に指摘される」との訴えあり、インデラル30mg/日を追加し、ふるえの訴えは少なくなった。T.A.さんは愛妻家で、奥さんの言う事は何でも聞いてあげたい、という方だ。臨床医である私にしても、患者さんのいろいろなお話を聞いて、少しでもその助けになりたいという思いで毎日の外来診療を続けている。大学病院にいると、3ヶ月に一回の外来になってしまって、こうはいかない。世間話をしている暇はないし、専門医として病気のコントロールが目的になってしまう。開業している地域の臨床医は、出来るだけ2週間に1回は外来に来てもらいたいと思って、それを実行している。小さなことでも、標榜科目以外でも「何でも尋ねて良い」と話しているので、細かいmanagementが出来るのだ。
3月11日「妻と歩いていてすり足になることがある」との訴えあり、FP錠を開始した。初期投与の1錠から3月24日には2錠として経過観察すると、次第に「すり足」の訴えは沈静化していった。
最近、心疾患患者の夫婦生活、外科手術後の性生活についていろいろな学会がコメントをするようになった。前立腺癌の術後や糖尿病女性患者についての不安や不満といった状況を、研究対象とする時代になったのだ。日本人は欧米人に比較して淡泊だといわれる性生活だが、そこまで踏み込んで調査した研究は見かけない。特に、パーキンソン病では自律神経障害があり、教科書的に性欲は低下していると考えられている。しかし、実際の所はどうなのだろう。
私は、時々患者さんに失礼にならない程度に、医師患者関係が完全に出来た方にsexについて聞くことがある。脳梗塞によって左上肢単麻痺になった60歳代の男性患者さんに聞いた時には「やってますよ。ぜんぜん問題ないです」との答えだった。先日来院した、脳出血後の血圧および体調管理で病院から紹介されてこられた70歳代の男性は、「週に一回やってます。男の大事な能力ですから。これがだめになったら私はお仕舞だと思っていますので」とご自分から話されたのに少しびっくりした。一緒に来られた奥さんは「私はそんなにしなくていいって言ってるんですけれど…」と多少困った顔をしていたが、夫婦として、夫に尽くしてあげたいという気持ちが強いようだった。
そんなこともあって、T.A.さんが「バイアグラを飲みたい」と訴えたことにも応えてあげたいと思った。私はあまりバイアグラを処方しない。というのも、病気によるインポテンツが原因でうまくいかない夫婦の営みに使うだけでなく、家庭外で使用する心積もりでいる患者さんもいて、いわば適応外処方になってしまうからだ。あの先生は簡単に出してくれるという評判が立つと、それを目的にやってくる患者が増える。使い方によっては心事故が起こったり、いつまでも勃起が続いて陰茎疼痛や血行障害が起きることもある。頭痛や嘔気、血液検査異常、眼痛、光視症なども不都合だ。専門的に日常使用している薬剤ではないので、処方するこちらのストレスになってしまう。
とりあえず、「和製バイアグラ」と神経泌尿器科の専門医が言っていた八味地黄丸を処方してみたところ、「少し元気になった」との反応があり、何とか希望に添えたかと胸をなでおろした。
その年の9月、「先生、今度北海道に行ってきます」とT.A.さんは外来診察時に話を切り出した。「飛行機で?」「いえ、バイクです」それも一人で行くというのだ。毎回受診するのにヘルメットを持って来ていたのを知ってはいたが、東京から北海道まで走って、道内を一回りしてくるというのだ。パーキンソン病の患者さんを多く見ているが、そんな人はいなかった。当たり前のことだが、T.A.さんは無事に帰ってきて、「先生にお土産」と塩辛を持って来てくれた。

翌年の4月には「花見でずいぶん飲み過ぎた」と飄々として話してくれる。6月には昨年と同じく、北海道にバイク旅行に行った。「先生、9日間で2000Km走ってきましたよ」と。こうなると、外来でじっと患者さんを待ちながら、毎日診察に明け暮れる私のような開業医より、よっぽど人生を謳歌していると言わざるを得ない。まあ、そのサポートを我々がしていると思えばそれはそれで意義のある人生を送っていると言ってもいいのかもしれない。
翌年の10月3日「やはりバイアグラを使いたい」とT.A.さんから話があった。前に書いた事情から、内科からは出せないが、いつもこの件でお願いをしている泌尿器専門医に紹介をするので行ってみますか?と問うと「是非紹介してください」とのことで、下北沢にある泌尿器科クリニックの院長に紹介状を持たせた。その後の外来に来たT.A.さんは、外連味もなく「行為は出来ました」と教えてくれた。
その翌年の3月4日、夜急に腹痛が起こり、クリニックはお休みだったから、奥さんに連れられて某大学医療センターを受診した。翌日まで外来精査を行い、急性虫垂炎の診断の元に入院となった。3月7日に外科に移り、全麻下で虫垂切除を受けた。
ある年の春、風邪症状で近医にかかった時に、問診でパーキンソン病だと話をしたらしい。小児科が専門のその医師は、パーキンソン病患者をあまり診たことがなく、とくにこんなにうまくコントロールされているパーキンソン病患者をあまり診たことがなかったのだろう、「そんな町医者でなくて、専門の先生に診てもらった方がよい」と、大病院を紹介されたという。「いや、私の主治医は専門の先生だから大丈夫です」と言ったが断わりきれず、「じゃあ行ってみます」と返事をした。大病院では神経内科の専門医が、MRI、MIBGシンチをやってくれて、「あなたの病気はパーキンソン病で良い」と言われたと報告があった。患者さんにとって良かれとやってくれたことだとは思うが、医療費の無駄遣い、時間の無駄遣い、地域で開業している神経内科医への冒涜行為、ということに、その先生は気付いてくれただろうか…。こうしてみると、地域の神経内科医をスポイルしているのは、むしろ地域の非専門開業医だという事が分かる。なんでも大病院に送ればよいという考え方を変えないと、地域医療の診診連携は進んでいかない。
こうしてNBMを実践している立場から患者さんのバックグラウンドを改めて見てみると、神経内科専門医としての診療のみならず、多くの患者さんの抱えている問題を解決し、その人らしい生き方を支える臨床医の姿が見えてくる。それは、エントロピーの増大という破壊へ向かう生命体としての人間の形を整え、時として壊れそうになる命を再び動的平衡の世界へと連れ戻す医師のartといってもいいのかもしれない。

